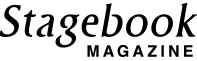はじめに
「どん底」とは、1901年から1902年にかけて書かれたマキシム・ゴーリキーの戯曲。当時ロシア社会貧民層が描かれる。貧民窟を舞台に住民の物語が展開する、史上初の【群像劇】とされる作品。日本では黒澤明氏による映画化も含め、繰り返し上演されている世界的名作戯曲である。
Twitter:@yusuke_kei
1984/4/23 生まれ 慶應義塾大学文学部卒業。 劇団新派所属、立松昭二門下。
学生演劇とアングラにどっぷりつかり、文学座に学ぶ。後、坂東玉三郎主演「ふるあめりかに袖はぬらさじ」「日本橋」に出演、薫陶を受ける。その中で、日本の古典を伝える新派の技や考えに魅せられ、H26新派入団。花形新派公演「深川の鈴」主演、他新派公演の他に「三婆」「芝桜」「牡丹灯籠」等外部出演も多い。演出作に「惜別のとき〜the long goodbye〜」など。観客投票型朗読コンテストにて、作演出も手がけた「バベルの家」「世界の片隅で」「青空の季節」が連続グランプリ。
本作にて新訳、翻訳劇の演出に初挑戦する。9月「オセロー」12月「有頂天団地」 @新橋演舞場出演予定。

蜷川幸雄氏との出逢い「好きなことを、好きなだけやれ。」
ー 演劇との出会いとは
桂 佑輔(以下、K): だいたいキッカケってあるじゃないですか。僕、ないんですよ・・・。ある日、ある瞬間にやろうと思ったんです。
中学生の時に学校帰りに鞄を持って、帰り道をふらふらっと歩いてたら、「あ、演劇やろう!」って。なにかがあってやり始めたというよりか、始めたことが先なんです。で、この歳まで続いているっていう・・・(笑)。もちろん紆余曲折はあったんですけど、始めたのはいいものの、中学生ですしね。男子校で進学校だったので演劇やることすら恥ずかしいこと(と捉えられる)くらい演劇の部活とかもなにもなくて・・・。
分からないから、何をしていいかも分からない。そもそも観たこともないし。台本どうすればいいのかとか、練習は何をすればいいのかとか、どうすればその道に進めるのかも。だから、これは知ってる人に聞きに行ったらいいだろう、と。たまたまなんですけど、こないだお亡くなりになられた蜷川幸雄さんが中学・高校の先輩だったんです。(当時は)なんにも分からなかったんですけど、蜷川幸雄さんという有名な方がいるらしい、世界的な評価も高い、きっと何か知っているに違いない。それで、蜷川さんにアポを取って、行って、「演劇って何をしたらいいんですか?」ってお聞きしたんです。そしたら、「好きなことを、好きなだけやれ。俺だって、好きなことを好きなだけやれてないんだ。」と。その後、お芝居を見せていただいたんです。その印象というか、鮮烈な思い入れみたいなものがとても残っていて、やっぱり原体験としてそれがあるのかなと思っています。
正直、“演劇”って意味分からなかったんですよ、難しいですし。なんかこう、人生が変わるような衝撃があったので。
その後は、お会いすることは叶わなかったんですけども、いまたまたまやっている舞台で蜷川組の方々と一緒なので、もっとちょっと早くお会いしたかったなぁ、なんて話しています。

ー その後、古典芸能の世界に踏み入られたのでしょうか?
K: それがですね、まだその時代はそうでもないんです。蜷川さんがやってらっしゃったことっていうのは常に頭の中にありましたし、僕は恩師の勧めでいわゆる20人、30人くらいしか入らない劇場だったりとか、そういったところに頻繁に足を運んでたんです。卒業してからも古典芸能、芸能というよりもどちかというとエンターテイメント、あるいは新劇って呼ばれるジャンルですよね。そういったものばかり観て・・・。
私自身、大学に通いながら文学座の養成所にいたんです。で、23、4歳のとき卒業して、その後5年くらいずっとアングラをやっていまして、たまたま坂東玉三郎さんとの出逢いがあって、玉三郎さんの演出の舞台、主演の舞台に出させていただきながら色々教えて頂いて。
その時に、「あ、古典芸能のエッセンスっていうものって、そういえば今まで自分が触れてきたことなかったな。だけど、こんな豊かな世界が広がっているんだ。」ってそうゆう感じ。ほんと初めて気づいて、逆にあんまり早く出会わなくて良かったなというか、ある程度新劇をやってたとか、西洋のものですよね、本来。だから、いま日本で主流なのが、イギリス演劇だったりとか、そういったところの教育法が入ってきて、アメリカのメソッドとかが入ってきていて、一生懸命勉強していった中で全く違う体系のものに出会って、それがなにかとても新しくて、また自分が迷ってる時期だったので、どうしたら自分を向上していけるんだろうかって迷ってた時期で、(その時に)「あ、全く体系の違うものを両方待ち合わせることはできないだろうか。」というもの考えたんです。
だから、日本の伝統的な芸能との出会いって、ここ5、6年のことでそこからもっともっと源流を辿っていきたい。僕はそのご縁で「新派」という様式美と生々しさが融合した明治・大正時代から続く劇団に入ったんです。そこに入って、お芝居をするようになりまして、源流辿っていきたいっていう想いで狂言であるとか、能であるとか、あるいは邦楽や舞踊だったり、そういったものには勉強はするようにしています。
ー 日本特有の手法と海外では具体的にどのような違いがあるんでしょうか?
K: そうですね。ま、よくごく一般的に言われているものとしては、「人」に焦点があたるいわゆる芸能と呼ばれるものは、日本のもの?「人に焦点があたるのが芸能である。作品に焦点があたるのが西洋なりアメリカ。」と聞いたことがあって、芸能体系とかいろんなものが違いますので、成り立ちも少しずつ違います。
西洋演劇でよくいわれるのは、対話構造。相手と自分の間で影響を与え合いながら、物語が転がっていく、その変化を楽しんでいく。
じゃあ、例えば歌舞伎や能、狂言、要するに日本の伝統芸能とか舞踊ですね。歌舞伎は、歌(=音楽)、舞(=舞踊)、伎(=技芸)である。やはり、それらを意識して観に行くので。舞台を通して、自分の人生になにか深い影響を与えることができた。これらはちょっと大きな差だとも思います。
ー 次回の「どん底」では、そういった手法もどんどん取り入れられている?
K: はい、積極的に取り入れています。「どん底」は特になんですが、もともと社会主義のプロレタリア文学の文脈で日本ではとても評価されることが多くて、思想なり手技手法のイメージ。今回もっとこう、彼らの生活はどこかというと、やっぱりロシアのものですから遠いイメージがあると思うんですよ。翻訳されている言葉選びが固かったり、そういうことがあると思うんですけれど、例えば日本で日本の作品を読むときに、遠い世界と思うことはあんまりないです。それは新派を観ても、歌舞伎を観ても、日本の言葉で書かれた日本のものを観ても、多少年代が離れているにしても、割と自分たちに近しい文脈で観てもらえると思うんです。手技手法に焦点を当てないで、彼らの生活に焦点を当てて、今回作っております。誰かと誰かが論理をぶつけて、ものを転がして行く。というシーンもあります。だけど、それよりも歌舞伎の世話物や、新派劇の風情を感じていただくような作り方をしています。
ー 観る側の心構えはそんなに不要ー?
K: もう、全然。翻訳劇を観に行くより、演劇を観に出かける。というほんとに気軽な気持ちで観られると思います。どちからというと、鑑賞するというより体験してもらう、というような。劇場体験をしてもらうような。劇場で目の前でやってものを受け取るんじゃなくて、もっと身近なもので、自分が空間の中に参加したような感じで観ていただけるんじゃないかなと思います。

初演のエモーションを伝える。日本の言葉一句、生活音で生々しく表現する。
ー 今回、再翻訳もされていると言うことですがー。
K: 翻訳をするということはどうゆうことなんだろうと。遠い時代の・地域・文化・言語、離れた土地のものを上演することにどうゆう意味があるのか。やっぱりそこにぶち当たってくる。どうしてもお客様がいることなので、好き勝手やっていればいいことではないと思っています。そう考えた時に、当時のロシアを再現することは一つのやり方としては素晴らしいことだとは思うんですけれど、現実問題我々の規模ではそれを完全に再現し得るだけのものが、経済的な意味でも不可能だと思うのです。そして、コンセプト上それを再現する必要がない。つまり我々が再現したいのは、現地で起こっていることをそのまま持ってくるのではなくて、その作品がお客様に与えたエモーション(=情動)が作品の本質であると捉えた時に、そのエモーションを持ってくるということなので、それをコーティングする様式はなんでもありだと思っているんです。一番大事なことは何かと考えると、そうなるのかなぁと思っています。
例えば、衣装、空間の設定、演技様式。今回、面(=おもて、仮面)をつけて出てくる俳優もいれば、白塗りして出てくる俳優もいます。音楽の使い方、例えば新派劇なども、音楽や生活音で場面を盛り上げていく。例えば、たまたま走ってくる汽車のシュッシュッシュッという音が本人の焦燥を表してるとか。それは音楽が流れくるというのは、すべて生活音なんですよね。あるいは、たまたま歩いていたら流しの三味線弾きがいたからそのシーンで三味線の音が聞こえてくる。遠くから常磐津が聞こえてきて、その歌詞がそのシーンにマッチしている。そういった日本的な音楽の使い方をしてます。津軽三味線にしても虐げられた弱い人たち。あれは元々、瞽女(ごぜ)の方々がやっていた音楽。虐げられた弱い人たちの叫びが聞こえてくるには何がいいのか。あるいは、心の内面がみえない、本音で生きてない人たちをどう表現したらいいのか。空間をある程度カオスにする、アングラ的に作っていくことによって懐がとても広がるので、そのシーンそのシーンその俳優ごとに、少し演技手法を変えていって、より本筋を浮き立たせたりとかできるんじゃないかと思っています。
ー このあとの稽古を少し観させて大丈夫ですか?
K: はい。ただ、かなり生々しいですよ。言葉使いなんかも全部。ロシアの古典の風も多少残してますけど、日本語って相手に合わせて主語・一人称が変わっていきますよね。英語だったら、全部「I」じゃないですか。でも、例えばある時代、明治大正近辺の江戸をとってみてもちょっと住む場所が違うだけで言葉使いが違うわけです。で、それだけでそのひとがどの階級どの階層、どの地域に住んでいる人なのかすぐ分かる。職人さんは職人言葉、深川だったら深川女(笑)、山手に住んでる人、武家の子供、全部言葉使い・イントネーションが違うわけなんですよね。文化圏が違うと、そういう生々しさ、生活感っていうのは表現することが難しい。そもそも(ロシアと)地域が違うので、まるっきり当てはめるわけにはいかないんですけど、でもそもそも文化も違う地域のものを持ってくるんであれば、より身近に感じていただくために、そういったものをあくまでも台本を別のものに改訂するとか、原案:ゴーリキーにはならない範囲でいろんなものを追加していけると思っています。
例えば、故郷から出てきて遠くモスクワの地にいるんだとすると、当然話す言葉は違うわけじゃないですか。あるいはこの人は職人階級だからこの言葉。暮らしに密着した生々しさを感じるんじゃないかと思います。いわゆる大和言葉という、生活に根差した言葉。「生活」という単語よりは「くらし」。柔らかいひらがなで表現できることばに直してますので、それぞれの生活感をことばから伝わってくるとー。
日本語を母国とするお客様がほとんどだと思いますので、初演のエモーションをどう伝えることが出来るか、ということに特化して今回は演らせていただきます。

ー 今回の「どん底」、どんなかたに観ていただきたいですか?
K: んー。劇場というのはなんの不安もなくて、完全無欠の人には用のない場所だと思います、本来。で、「どん底」の人たちっていうのは、17人出てくるんですけどそれぞれが強さと弱さを抱えていて、いかにどん底のひとといえど我々と変わることがない「人間」であって。そうゆう人間の生き様っていうのはとても清々しいものだと思うんです。悲劇的な終わりを迎えますけど。その悲劇であったとしてもとても清々しいものだし、この作品が書かれた時に当時の劇作としてとても新鮮だったのは、それまでは王侯貴族なんかの特別なスペシャルな人間たちが主人公だったんです。だけど、この作品でゴーリキーが全く主役たりえない人たちを書いた。それはとてもセンセーショナルで。生きている人間の魂、願いなのかな。きらびやかものではなくて、生々しい土のついた感じ。
歴史というのは、もともと坂本龍馬が作ったわけでも、徳川家康が作ったものでもなくて、草の根で人々が作ってきたものですから、そういった歴史を体感してもらいたい。人間というものに対して、清々しい希望を持てるような、祈りを先の時代に持っていけるような。笑って泣いてスカッとしては決してないんですけど、なんか大事なすごく壊れやすい砂糖菓子みたいなものを胸に抱いて帰っていただけるようなものになると思うんで、そうゆうものを欲しいなって思う人にはぜひ観ていただきたいです。
取材・文:尾中力也
撮影:川端一生
提供:根ぎし 笹乃雪
劇團旅藝人「どん底」

1902年、「熱狂と笑いをもって迎えられた」モスクワ芸術座初演。
それまでの演劇の常識を覆す「17人の何ら主役たりえない下々の人々」が織りなす、いわば史上初めて世界に誕生した群像劇。
「the新劇の古典」を、今回、本公演の演出に特化して翻訳を全編見直し、小劇場→新劇→「the和物の古典」劇団新派在籍の異色の若手が演出します。
ノーカットにこだわり、初演の衝撃とエモーションをいま東京で体感していただくべく、日本の古典や様々な様式を取り入れて「生き生き」上演します。
「生き生き、ゴーリキー。」
敢えて演劇的育ちがバラバラの17人の出演者達。
きっと、役を纏ってスパークする17人の人生やパワーに、生きていることを実感していただけることでしょう。
ウェブサイト
https://www.donzoko.info/
日程
10月4日(木) 11:30 /18:00
10月5日(金) 11:30 /19:00
10月6日(土) 11:30/ 18:00
10月7日(日) 11:30
劇場
ザムザ阿佐谷
〒1660001 東京都杉並区阿佐谷北2-12-21 ラピュタビル B1F
チケット代
全席自由 3,800円
脚本
原作 マキシム・ゴーリキー
翻訳・演出
桂佑輔(劇団新派)
出演
嶋隆静(オフィスSHIMA)
加納明(㈱エム・ケイ・ツー)
富真道
飯尾広海
俊えり
福田英和(ダブルフォックス)
中島佐知子(ULPS)
家紋健大郎(㈲宝井プロジェクト)
糸原舞(㈲優企画)
野村龍一(天才劇団バカバッカ)
長紀榮(プロジェクトGKK.C)
雅楽川巖
狩野美彩子(ダブルフォックス)
松谷聡達(㈱ブラッシュアップ・ワン)
山口祥平(碗プロダクション)
小島健吾
邱太郎(オフィス松田)
スタッフ
舞台美術 : 尾谷由衣
照明 : 大島孝夫
音響 : 余田崇徳
衣裳・小道具 : 大出茉莉
ステージング : 美幸ちひろ(トゥフロント)
舞台監督 : 原義則・宇佐美裕志(舞台猫乃手)
コピーライター : 和泉伸吾(アシロジ)
アートディレクター : 石川桃子(アシロジ)
フォトグラファー : 縄倉琉璃子
制作事務 : 石坂悦子
制作 : 伊佐あつ子